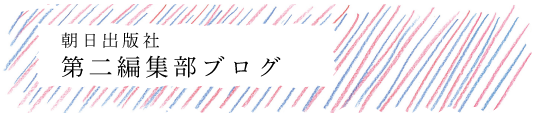中川恵一
イラスト 寄藤文平
イラスト 寄藤文平

25 発がんリスクの代表例――甲状腺がんの基礎知識。
チェルノブイリの原発事故では、白血病など、多くのがんが増えるのではないかと危惧(きぐ)されました。しかし、実際に増加が報告されたのは、「小児の甲状腺がん」だけでした。小児甲状腺がんが増加した最大の原因は、旧ソビエト政府が、当初、事故を認めず、初動が遅れた点です。この点、福島第一原発では、まずまず適切な対処がなされてきたと言えます。
放射性ヨウ素(I‐131)は、体に入るとその30%程度が甲状腺に取り込まれます。これは、甲状腺ホルモンを作るための材料がヨウ素で、甲状腺がヨウ素を必要としているからです。
普通のヨウ素も放射性ヨウ素も、人体にとってはまったく区別がつきません。物質の性質は、放射性であろうとなかろうと同じだからです。たとえて言えば「食べ物があったので食べてみたら、毒針がついていました」ということなのです。
ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に不可欠ですが、その摂取のほとんどが海草からのものです。チェルノブイリのように地理的に見て海草が少ないところでは、常に甲状腺はヨウ素をほしがっている状態です。そこに、天然には存在しない放射性のヨウ素がやってきたので、どんどん取り込まれてしまいました。
日本人はふだんから海草や海産物を食べているので、日本人の甲状腺は、チェルノブイリの人たちに比べれば、普通のヨウ素で満たされた状態にあります。だから、放射性ヨウ素の取り込みも少なく、チェルノブイリほどの影響はないだろうと考えられます。
放射性ヨウ素の場合、放射されるベータ線は、線源から2ミリくらいのところで止まってしまいますから、甲状腺という組織が「選択的」に照射されることになります。結果的には「局所被ばく」の一種だと言えます。
なお、甲状腺がんの放射線治療(放射性ヨウ素内用療法)では、3.7ギガベクレル(3.7×102Bq「ギガ」は10億!)という強い放射性ヨウ素を口から飲み込むのですが、それでも全身への影響がほとんどないのは、放射線ヨウ素が甲状腺に集まり、全身への被ばくを抑えるからです。
チェルノブイリの子供たちは、避難や食品規制の立ち後れから、放射性ヨウ素に汚染されたミルクを飲んでいました。子供の細胞分裂は活発で、放射線による発がんリスクが高いため、小児の甲状腺がんが増えたものと思われます。
なお、がんはできる部位(臓器)や進行度(ステージ)によって千差万別ですが、甲状腺がんは、がんの中で、もっとも治癒しやすいがんです(治療後の5年生存率は95%以上)。

26 チェルノブイリ、スリーマイル島で起きた健康被害。
1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所4号機で起きた爆発事故では、広島に投下された原子爆弾400発分の放射性物質が放出されました。
当時、旧ソビエト政府は住民のパニックを恐れ(冷戦下でもあり)、この事故を数日公表しなかったため(もちろん避難指示もなく)、近隣の村は大量の放射性物質をあびることになりました。
事故後の復旧作業にあたった作業者53万人の平均被ばく線量(全身=実効線量)は117ミリシーベルトに上りました。避難した近隣住民11万5千人の平均被ばく線量は、全身(実効線量)で31ミリシーベルト、甲状腺では490ミリシーベルトと報告されています。さらに、チェルノブイリに近い、ベラルーシ、ロシア、ウクライナの640万人の住民については、全身で平均9ミリシーベルト、甲状腺で102ミリシーベルト、その他の全ヨーロッパ(トルコ、コーカサス、アンドラ、サンマリノを除く)では、それぞれ、0.3ミリシーベルト、1.3ミリシーベルトと見積もられています(国連科学委員会〔UNSCEAR〕2008年報告附属書D)。
この事故による小児甲状腺がんの発症は、国際原子力機関(IAEA)の公式見解では、2006年までに発見された患者さんが4千人、死亡が確認されたのは9〜15名、とされています。
事故の正式発表や避難措置が遅れ、放射線に汚染された飲食物が規制されず、甲状腺に特異的に放射性ヨウ素が集まったため、人為的・必然的に起きたことでした。
1979年3月28日、アメリカのペンシルヴェニア州スリーマイル島の事故では、①減速材(放射線、詳しくは中性子線のエネルギー放出を抑えるための資材)として水を使用していた、②核分裂は停止していた、③格納容器があった、ということで、福島のケースに近いことがわかります。長期の詳細な調査が行われましたが、事故が、住民の健康に有意な影響を与えたという結論は出ていません。
福島第一原発の事故は、4月12日、国際的な事故評価尺度(INES)で「深刻な事故」とされるレベル7に引き上げられました。チェルノブイリと同一レベル。ただし、放射性物質の外部への放出量は1けた小さいとされます。国際原子力機関(IAEA)は「レベルは同じでも、事故の構造や規模ではまったく異なる」とコメントしています。

27 がんの放射線治療にみる放射線の影響。
放射線は目に見えず、匂いも音もせず、線量によっては人体に致死的な影響を与えるため、十分な配慮を持って扱わなければなりません。
福島原発の事故は、いったん放射性物質のコントロールを失うと、どれほど扱いがむずかしいものかを教えてくれます。
ただ、現在の私たちの生活は、原子力発電所による電力供給以外にも、製造業や農業で、放射線の“恩恵”を背景に、営まれています。医学もその一部です。
私の本業の「がんの放射線治療」を(ごくかいつまんで)ご紹介しながら、放射線被ばくの問題を考えてみたいと思います。
放射線の量が多くても、照射されるのに要する時間が十分に長ければ、また、放射線がかかる範囲が小さければ、身体への影響はほとんどみられません。このことを私は、毎日の診療の中で経験しています。
実際、人間は全身に4グレイ(Gy)(=4シーベルト=400万マイクロシーベルト)の放射線を一度にあびると、60日以内に50%が死亡すると言われていますが、私たちががんを治すために患者さんに投与する放射線量は多くの場合、50〜80グレイ(=50〜80シーベルト=5000万〜8000万マイクロシーベルト)という量になります。それでも、患者さんは、日常生活を続けながら外来通院で放射線治療をすることができます。
これほどの大量の放射線を、患者さんに治療として投与できるのは、何回にも分けて放射線をかけていることと(普通は1回あたり2〜3グレイ=2〜3シーベルト=200万〜300万マイクロシーベルト)、全身ではなく必要な範囲だけに放射線をかけていることが大きな理由です。
放射線を何回にも分けて照射することを「分割照射」と言います。これによって、正常な細胞の放射線によるダメージを回復させながら、がん細胞をたたくことができるのです。よく、患者さんに、「何週も通うのは大変だ」と言われますが、分割照射によって、放射線治療は「カラダにやさしいがん治療」になっているのです。
一方、放射線治療の副作用は、放射線が、かかる範囲によっても違ってきます。最近テレビや新聞記事などでも多く取り上げられるようになっている「ピンポイント照射」という方法を使えば、10〜20グレイといった大線量の放射線を1回で照射することもできます。
仮に、がん細胞だけに完全に放射線を集中することができれば、放射線を無限にかけることができます。副作用はゼロで、がん病巣(びょうそう)は100%消失することになります。今でも、この「理想」は夢ですが、かなり現実的になってきました。
実際に、ガンマナイフという治療装置を用いたパーキンソン病に対する「定位的視床(ししょう)破壊術」では、きわめて限られた範囲に13グレイという超高線量を1回で照射することもあります。この放射線は、もし全身にあびれば数日後には死亡してしまうほどのものです。

第9回へ
(続く)
[著者紹介]